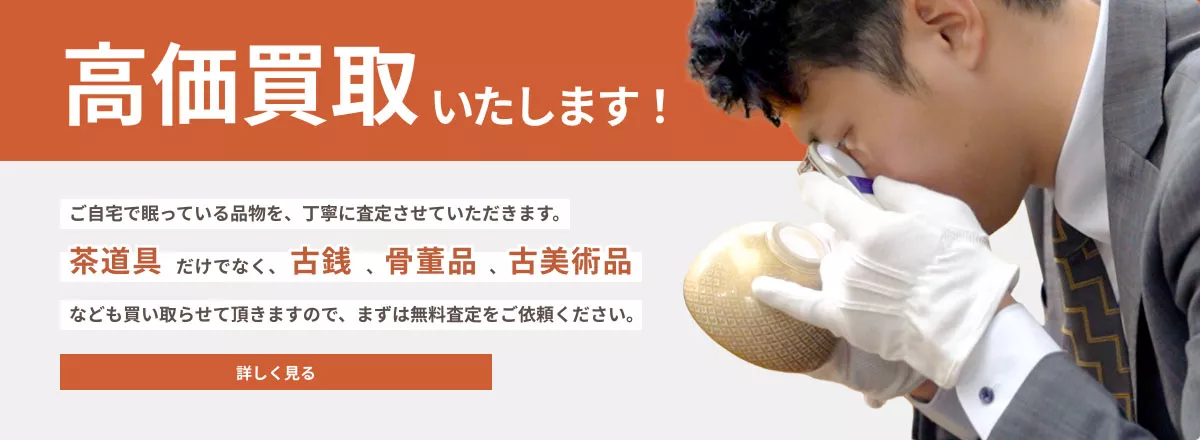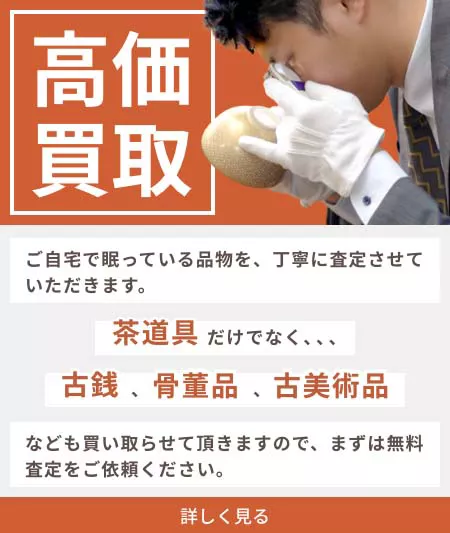最新情報
< スタッフブログ >
松阪萬古の歴史
ギャラリー森田は松阪市で明治27年創業の老舗茶道具店です。茶道具販売だけではなく高価買取りも承ります。
今回は、松阪市で生産され「三重県指定伝統工芸品」として指定されている松阪萬古の歴史をご紹介します。
1716年(享保元年)~ 1804年(文化元年)
和泥斎寸丈(植松庸知(やすとも))寸丈焼(時中焼)開窯
裏千家八代一燈が松阪の陶工・二代和泥斎時中丈七を伴い徳島を訪れ、阿波焼を興す
一燈、阿波焼で阿波筒花入を御好みになる
1855年(安政二年)
竹川竹斎(玄々斎門下)射和萬古開窯
1863年(文久三年)
射和萬古閉窯
1856年(安政三年)
初代信春 百々川焼開窯
1863年(文久三年)
下村焼(四ツ又焼)開窯
1878年(明治十一年)
二代芳春 錦花山焼開窯
徳和焼と改称(長谷川可同命名:又妙斎・円能斎門下)
1914年(大正三年)
三代芳隣 松阪萬古と改称(昭和十年小津笹川庵命名)
淡々斎宗匠より御好窯として「松古」の印を賜り「松古窯」と命名される
1916年(大正五年四月)
玄句斎格式披露茶会三重県津市で開催
1947年(昭和二十二年)
四代勝山 即中斎宗匠の御用を承る
1998年(平成十年)
芳山五代目を継承
古萬古の赤絵・盛絵技法を研究
2006年(平成十八年)
喜寿記念展示会開催
店舗アクセス
株式会社ギャラリー森田
企業概要- 所在地
- 〒515-0083 三重県松阪市中町1948
- 電話番号
- 0598-21-3178
- 【 お車でお越しの方 】
- 伊勢自動車道 松阪IC下車
- アクセス道路で松阪市内へ 松阪ICより約10分
- 【 電車でお越しの方 】
- 近鉄松阪駅より徒歩10分